妊婦の栄養状態と、生まれた子の生活習慣病のなりやすさとの関係を検証するため、妊婦200人を対象とする世界的にも珍しい調査を国立国際医療研究センターと早稲田大学総合研究機構が今月から始めるという報道発表が2012年5月10日にありました。
生活習慣病といえば、その名の通り日々の生活に改善を要する病気というイメージがあり、またかつては「成人病」とも言われていたことから考えると、子供さらには妊婦を対象とした調査が実施されると聞いても、いまひとつピンと来ませんでした。
しかし、調べてみると「近年英国を初めとする欧州を中心とした疫学研究から、胎生期から乳幼児期にいたる栄養環境が、成人期あるいは老年期における生活習慣病発症リスクに影響する可能性か指摘されDevelopmental Origins of Health and Disease(DOHaD)という概念か提唱されている」(「日産婦誌60巻 9 号」)のだそうです。
DOHaD学説に対応する日本語訳は、定着したものはないようですが「成人病胎児起源説」「や「胎児プログラミング仮説」などとも呼ばれ、この理論を1980年代にはじめて提唱したDavid Barker, M.D氏の名をとってBarker説とも称されます。 これは、「胎生期から乳幼児期に至る栄養環境が、成人期あるいは老年期における生活習慣病発症リスクに影響する」という考え方で、「胎児期に低栄養環境におかれた個体が、出生後、過剰な栄養を投与された場合に、肥満・高血圧・2型糖尿病などのメタボリックシンドロームに罹患しやすくなる」というものなのだそうです。
母体が妊娠中に十分な栄養を摂らなかったり、何らかの異常があった場合には、胎児は少ない栄養で生存する「倹約体質」の仕組みをつくってしまい、出生後もこの仕組みが持続。そのため、栄養を撮り過ぎると肥満や2型糖尿病になりやすいと考えられているそうです。
日本では、20代および30代の妊孕世代女性のBMIか急速に低下しており、不自然なタイエットによるやせの増加か顕著だと言われています。このようなやせた女性が妊娠した場合、低出生体重児を出産するリスクか高いと報告されています。
しかし、一説には妊娠中ではなく更にさかのぼり受精時にも女性が十分な栄養を摂取しているかどうかも、胎児に影響を及ぼすとも言われています。
このような、母体の栄養状態と子供の胎生期から乳幼児期にかけての経過を調査することで、生活習慣病発症との因果関係を立証することが目的のようです。
既に、生活習慣病を患う立派な「大人」たちにとっては、「今さら」「時既に遅し」なんて思ってはいけません。
お子様やお孫さんたちが身ごもる年代になってくる今、よきアドバイスができる存在になれるよう、ご参考までに。
参考文献
朝日新聞デジタル 【医の手帳】生活習慣病(1)
http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001205210001
日産婦誌60巻 9 号
クリニカルカンファレンス7 妊娠中の栄養管理と出生児の予後
3)胎生期から乳幼児期における栄養環境と 成長後の生活習慣病発症のリスク http://www.jsog.or.jp/PDF/60/6009-306.pdf

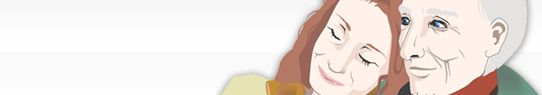
ツイート
mixiチェック